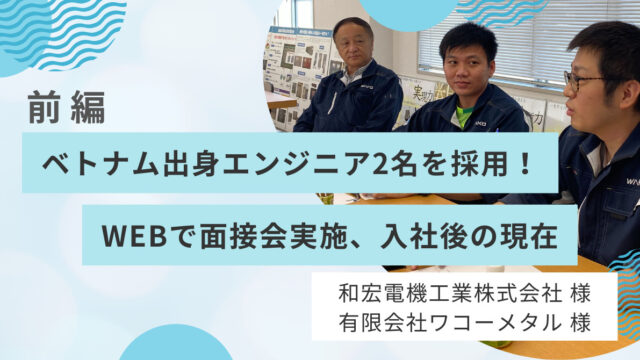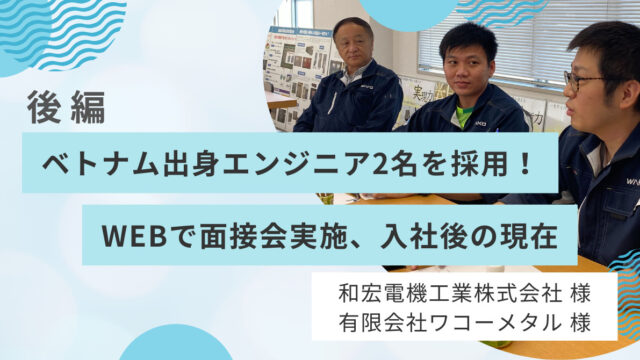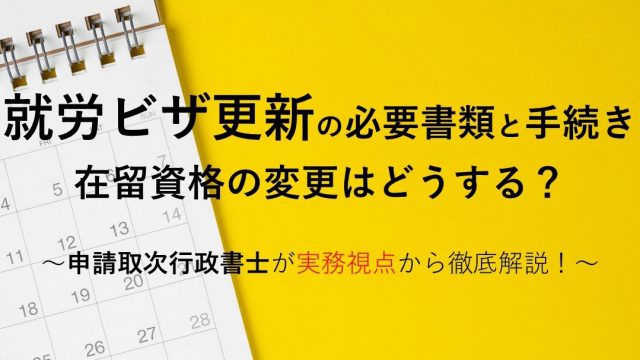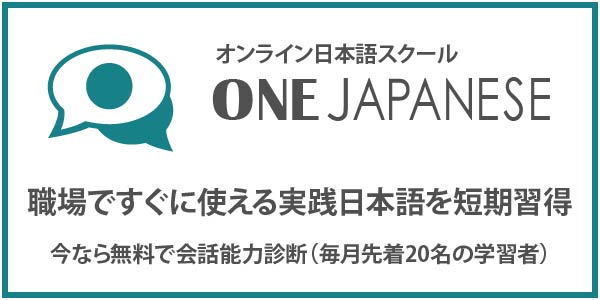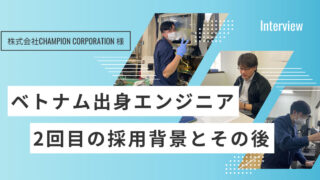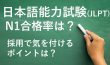【文部科学省国費留学生協会 会長 Austin Zeng氏】
―――はじめに、個人もしくは所属団体の活動内容について教えてください。
私は文部科学省国費留学生協会(略:MSA)の会長をしております。私が来日した10年前の時に、学生が日常生活や就活に関する情報伝達がなされず放置状態になってしまっている状態でした。来日後にコミュニケーションが絶たれてしまい、互いの繋がりも維持されず、学生達が必要としている情報が行き届かないという問題があるのです。また、特にキャリアに関して日本型就活の不透明性が高く、日本語以外での言語で情報伝達がなされない点などもあり、実際大学院で最先端の研究に取り組んだ学生でも仕事に就けないケースは多々ありました。この状態は、当の留学生にとってだけではなく、「日本留学」というブランド、そして日本で働きたい人が仕事が見つからないという観点から、日本社会全体にとって非常にもったいない状態だと感じました。
その問題を解決したいと考え、2016年に団体を共同創立しました。現在、留学生・卒業生のキャリア支援での活動内容としては、就活や日本国内での起業、さらに就職・転職などのキャリアに関するウェビナー開催や人材会社と共同でのイベント開催を行っております。
また、私個人の活動ですが、日本の就活情報や採用システムに関する個人ブログを執筆しております。その他に、日本在住の外国人留学生の就職状況に関する調査も経済産業研究所などの機関で行っております。外国人分野以外の活動ですと、私の本職はエンジニアであり、その他にもWeb開発や翻訳、通訳を兼業しております。
―――ありがとうございます。文部科学省の奨学金を受け取っている方々は、今ではコミュニティがあるのでしょうか。また、過去コミュニティに属していなかった方々とはどのように繋がれば良いのでしょうか。
もともと、これといったコミュニティはありませんでした。仕事を通して、その都度お会いする形でした。現在、MSAのプラットホームにフォローしている人数は延1万3千人を超え、少なくても国内であれば文科省の国費留学生に関しては私達はそのコミュニティーの役割を果たしているでしょう。
一方で、海外に帰っている方たちは、元日本留学生・卒業生団体を通して繋がることができます。
―――文部科学省の国費で来日されている方はどういった基準で選ばれているのでしょうか。また、その金額と、その制度の目的を教えてください。
まず、制度の目的から言うと、制度自体は昔からあるものなのですが、現代の目的で言うと、世界の優秀な人材を日本に呼び込むこと、また、日本の大学の国際化を促進させることの二点です。コロナ前では、毎年3000人強の留学生が来日しており、奨学金は授業料免除に加え1ヶ月あたり11~14万円程度です。審査基準は、憶測ではありますが、外交上の重点地域に重きが置かれていると思われます。結果、東南アジアが多いですね。その上で、日本語と英語、理系であれば数学の成績等が審査基準になっています。そして、3000人強の留学生のほとんどが大学院生なのですが、彼らの研究分野が何か、受け入れている教授がいるかどうか、さらに研究分野の斬新さが審査基準になっているのではないかと思います。
―――では、現在のサービス内容について、将来的にどのように拡充を図っていきたいとお考えですか?
まず、はじめに協会の強みを申し上げたいと思います。ここまで外国人学生の新卒向けに就活についてのウェビナーをこれだけ開催している団体は他にはないと思います。では何故、新卒の就活サポートに取り組んでいるかというと、初めの仕事に就くのは大変なことであるのに加え、本来スキルベースで評価されれば優秀な方が、日本独特の採用方法のために就職できなかったというケースが多く、その問題解消に向けたサポートをしたいと考えたからです。大学によって学内のキャリア支援を施している学校もありますが、今までは学校個々に小さなコミュニティで、低頻度での開催でした。大学の垣根を跨っている協会だからこそ、オンラインでのウェビナー開催を通して、どの大学の学生かは関係なく、自由に参加できる場を作りたいと考えています。
さらに、去年から新しい取り組みとして「レジュメバンク」というものを始めています。それは、就活生のレジュメを集めて、許可を取った上で日本の人材企業パートナーに連携するという仕組みです。今後はサポート対象として、転職層や第二新卒層にまで手を伸ばしていきたいと考えております。
―――なるほど、ありがとうございます。それでは、トップ層の優秀な外国人学生を受け入れたいと考えたときに、日本企業側が気を付けないといけないことは何でしょうか。また、優秀な学生から選ばれる企業になるためのポイントは何でしょうか。
外国籍社員を雇用する際の一つの課題として、日本語能力の有無が挙げられると思いますが、日本語能力は基準の一つとしてあっていいと思います。というのも、日本語能力を基準から外したとして母集団は確かに増えると思いますが、実際に基準から外した結果、現場で外国籍社員が仕事に付いていけなくなり、失敗してしまった実例もあります。ただその一方で、母語社並みの完璧な日本語ということを求めるべきかは別の問題で、今の多くの企業は業務に必要以上な日本語を求めているというふうに感じます。
さて、留学生に対しての魅力訴求ですが、以前行った調査結果としても出ているのですが、最も学生が求めているのは「学び」があるかどうかです。また、専門分野を活かせられるかどうかも重要視している傾向があります。その二点をアピールすることで優秀な学生を獲得できると思います。これまで、就活説明会を見ていると日本企業側は日本人目線で強みをアピールしていますが、そこは外国人の学生側が求めていることとズレが生じているように感じます。
―――優秀な海外人材を獲得しきれていない日本企業へ伝えたいメッセージはありますか?
失敗を恐れないでほしいですね。失敗しないと成長はありませんので、一度試してみてほしいです。
現代では「多様性」「ダイバーシティ」といったワードが社会で流行し、外国人採用をしている会社は増えましたが、ダイバーシティー以前に何よりもビジネス的観点で言いますと、日本人だけの企業は非常に危険だと伝えたいです。日本語で企業に入ってくる情報は世界から見ると2~3年遅れのものが多く、本質的な多様性を持たない企業は情報弱者になってしまいます。それは、ビジネスとして大きな機会損失となります。海外マーケット状況や海外の脅威についての情報をいち早く獲得するために、異なった視点を持った人材を入れることは大事です。それこそが外国人社員を雇う意義だと思います。
ただ、試している中で、一つ留意してほしいことがあります。外国籍社員を数人雇っただけでは企業に多様性がつきません。追加の工夫をしないと、外国人側は圧倒的少数派となり、多数派に圧倒されてしまいます。また、「てにをは」を間違ったとしても、その人たちの意見を正しく評価することに対する留意も必要です。雇ったことで終わりにするのではなく、このように彼らの声を積極的に拾うなり、その人たちがきちんと声を出せる状況、そしてその声を吸い上げる環境を整えるところまでが重要だと考えます。

「外国籍社員受け入れに必要な入国前後の準備」をダウンロードいただけます。
資料についてのご質問はお問い合わせぺージよりご連絡ください。